アレルギーの一種「花粉症」とは?
花粉症とは、アレルギー反応の一つです。アレルギーとは、体外から侵入してきたウイルスや細菌などの異物から体を守る“免疫機能”が過剰に働き、さまざまな症状を引き起こす病気のことを指します。
スギの花粉症を例に挙げると、本来は体に無害なスギ花粉に対して免疫機能が過剰に反応して、体外に追い出すためにアレルギー症状が引き起こされるのです。
花粉症の症状
花粉症になると、おもに以下のような症状がみられます。
- 【アレルギー性鼻炎】
- ・ 鼻水
- ・ 鼻づまり
- ・ くしゃみ など
- 【アレルギー性結膜炎】
- ・ 目のかゆみ
- ・ 涙が出る
- ・ 目の充血
- 【その他】
- ・ のどのかゆみ
- ・ 皮膚のかゆみ頭が重い
- ・ 頭痛
- ・ だるい
- ・ 熱っぽい
- ・ 寒気
- ・ イライラ
- ・ 消化不良
- ・ 食欲不振
また、鼻づまりが悪化すると、副鼻腔炎(鼻のなかに膿がたまる状態)になる場合があります。近年、増加しているヒノキの花粉症では、スギ花粉よりも粒子が細かいためのどの粘膜に付着しやすく、せきや息苦しさなどの症状が生じやすいと報告されています。
花粉症の種類
花粉症を引き起こす植物は、現在50種類ほどが確認されています。日本でのおもな花粉症の種類と流行時期は以下のとおりです。
- ・ スギ (2~4月)
- ・ ヒノキ (3~4月)
- ・ ハルガヤ (4~7月)
- ・ カモガヤ (4~7月)
- ・ ブタクサ (8~9月)
花粉症の症状が現れるまでの期間には個人差がある
花粉にさらされたからといって必ずしも花粉症の症状が現れるわけではありません。花粉症の症状が現れるまでの期間は、花粉にさらされ続けた頻度や量に影響を受けます。環境省や日本気象協会が発表している花粉飛散情報を確認して、マスクやメガネなどで花粉を取り込まないようにする工夫をしましょう。
花粉症と食べ物の関係

実は花粉症は、毎日口にする食べ物によって、悪化したり改善したりする場合があります。
花粉症は「栄養の偏り」で悪化しやすい
栄養の偏りは免疫機能の低下を招き、アレルギー反応を引き起こしたり、悪化させたりします。アレルギー反応の一つである花粉症を予防するには、栄養をバランスよくしっかり取って「免疫機能」を正常に維持する工夫が必要です。
不足に気を付けたい栄養素
花粉症対策のために、以下の栄養素不足に注意しましょう。
・「ビタミンA」
ビタミンAは、粘膜を正常に保つ働きがあり、免疫機能を高めてくれます。
・「ビタミンB6」
ビタミンB6は、過剰な免疫細胞の働きを抑えて、アレルギー症状を予防したり緩和したりする効果があります。
・「ポリフェノール」
ポリフェノールは、抗酸化作用があります。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールには過剰な免疫の働きを抑える効果があるとされ、アレルギー症状の予防や緩和に役立ちます。
花粉症は「腸にやさしい食べ物」で予防・改善が目指せる
花粉症などのアレルギー症状の重症度は、腸内環境に左右されます。腸内環境が悪ければ悪化しやすく、よければ予防・改善が期待できるのです。体内にある免疫細胞の約70%は“腸”に存在しているため、腸内環境がよければ、免疫機能は正常に働きやすくなります。
腸の中にはさまざまな働きをする免疫細胞が多く存在します。免疫細胞の中には過剰な免疫の働きを抑える細胞があり、免疫機能の過剰な反応によって引き起こされる花粉症などのアレルギーを抑える役割を担っているのです。
腸内環境がよい状態とは、善玉菌が悪玉菌よりも多い状態をいいます。一方で、腸内に棲む善玉菌が不足すると、腸内環境は崩れ免疫機能のバランスが崩れ安くなります。すると、花粉症を発症しやすくなったり、症状が悪化したりするのです。
腸内に棲む善玉菌である「乳酸菌」や「ビフィズス菌」を含む食べ物や善玉菌のエサとなる「オリゴ糖」や「食物繊維」を含む食べ物を積極的に摂って、腸内環境を整えましょう。
花粉症の人におすすめな食べ物や飲み物
花粉症の辛さを緩和するために、おすすめの食べ物や飲み物があります。ただし、薬とは違って、食べたらすぐに効果が出たり、治ったりするものではありません。あくまで食品なので、補助的な対処法として毎日まんべんなく食事に取り入れていきましょう。
免疫機能の維持におすすめな食べ物
正常な免疫機能の維持が花粉症の予防、症状緩和に役立ちます。
- ・ 大葉
- ・ 青魚
- ・ トマト
- ・ ヨーグルト など
体を温める食べ物
体を温めて血行を良くすると鼻水や鼻づまりなどの症状が緩和しやすくなります。
- ・ ニラ
- ・ ねぎ
- ・ しょうが
- ・ 大葉
- ・ ウド
- ・ フキ
- ・ シナモン など
乾燥予防におすすめな食べ物
鼻やのどの粘膜が乾燥すると花粉が侵入しやすくなるため、乾燥予防は花粉症の症状を抑える効果が期待できます。
抗酸化成分を含む食べ物や飲み物
体の老化を促す活性酸素が活発になると、炎症やアレルギー反応が進行しやすくなるとされています。そのため、以下のような抗酸化成分を含む食べ物や飲み物がおすすめです。
- ・ 鶏レバー
- ・ ウナギ
- ・ にんじん
- ・ かぼちゃ
- ・ ピーマン
- ・ ブロッコリー
- ・ オレンジ
- ・ アーモンドといったナッツ類
- ・ 緑茶
- ・ 甜茶 など
花粉症を悪化させるおそれのある食べ物や飲み物
摂取する食べ物や飲み物により、花粉症を悪化させてしまう場合があります。
以下の食べ物や飲み物には注意が必要です。
トランス脂肪酸を多く含む食べ物
トランス脂肪酸を摂り過ぎると、アレルギーを引き起こしやすくなると報告されています。マーガリン・ショートニング・ファットスプレッドにはトランス脂肪酸が含まれている場合がほとんどです。市販されているパン・クッキー・ケーキといった洋菓子や、揚げ物などの原料に使用されている場合が多いので注意しましょう。
刺激の強い食べ物
刺激物は、粘膜にダメージを与えて鼻や口から花粉が侵入しやすくなる可能性があります。粘膜に刺激になるような香辛料は控えるのがいいでしょう。
アルコール飲料(お酒)
お酒は、花粉症の症状を悪化させます。お酒に含まれるアルコールにより毛細血管が拡がり、鼻の粘膜が腫れてしまうのです。すると、鼻づまり・鼻水・くしゃみの症状が強くなります。
また、体内でアルコールを分解する際にできるアセトアルデヒドがアレルギー症状を引き起こすヒスタミンの産生を促すため、飲み過ぎには注意しましょう。
花粉症対策におすすめの食べ物を毎日食べる工夫
花粉症は、命に関わる病気ではありませんが、自然に治るケースはほとんどありません。花粉症を改善するための近道は、症状に合わせた適切な治療です。医療機関では、症状に合わせて医師が薬を処方できます。症状が気になる場合は、早めに医療機関へ受診しましょう。そのうえで、毎日の食事での健康の基盤づくりが大切です。
意識して花粉症対策におすすめの食べ物を買う
当たり前ではありますが、まずは食材を手元に用意するところから始めます。食材が自宅にあれば、「腐る前に食べなければ」という意識が向くため効果的でしょう。
ルーティーンを作る
食べるタイミングのルーティーン化により、おすすめ食材を無理なく食べる習慣が作れるでしょう。まずは意識して選び、習慣化していきましょう。
- ・朝ごはんのデザートにヨーグルトなどをチョイスする
- ・ごはんにはゴマをかける
- ・麺類や冷奴には、大葉・ねぎ・しょうが・みょうがを添える
- ・間食には、ピーナッツや干し柿を食べる
花粉症改善のために5つの生活習慣見直しポイント
花粉症改善のため、食事改善と並行してとり入れたい生活習慣のポイントを5つご紹介します。
自分を労わる習慣を
ストレスは、花粉症の大敵です。免疫機能のバランスを崩し、花粉に対する過剰反応につながる可能性があります。日ごろから、「疲れたら休む」「趣味を楽しむ」といった自分を労わる習慣でストレスをためないようにしましょう。
早寝を心がける
睡眠不足も花粉症の大敵です。免疫機能のバランスを崩し、花粉に対する過剰反応につながる可能性があります。花粉症の症状で寝つきが悪い場合は、「空気清浄機で花粉を除去する」「寝る前に入浴する」といった方法で、寝やすい環境づくりをしましょう。
タバコを避ける
タバコの煙は粘膜を刺激するため、鼻づまりの悪化を招きます。喫煙者本人だけでなく、周囲にいる人が吸う煙も悪影響があるため、注意が必要です。タバコが避けられない場合は、空気清浄機で煙を除去したり、マスクを着けたりして対策をしましょう。
家の中に花粉を持ち込まない
外出した衣服には花粉が付着しています。家の中に持ち込まないように、衣類を払い落としたり、粘着テープや湿った布巾でやさしく花粉を取り除いたりしてから家に入りましょう。衣服を払い落とすときは花粉が舞い上がり吸い込んでしまう可能性があるので要注意です。また、帰宅後は、直ちに部屋着に着替えましょう。
室内または午前中に適度な運動を
運動不足も、花粉症の悪化につながる可能性があります。体力と免疫機能の低下を招き、花粉に対する過剰反応への懸念があるのです。プールやジムでの室内運動や、比較的、花粉の飛散が少ない午前中にウォーキングやランニングといった運動を取り入れてみましょう。
花粉症改善には対策の継続が大切!早めに治したい人は受診が一番
花粉症は、アレルギー症状の一種であり、本来は身を守るために働いている「免疫反応」が過剰に起こり、体に悪影響を与えている状態です。
日常の中で、免疫反応を正常に保つには、毎日の食事に気を配るのが効果的でしょう。
ただし、食べ物は薬とは違い即効性はありません。乳酸菌やビフィズス菌の補給、栄養バランスのよい食事は、毎日続けていく習慣化が大切です。
辛い花粉症を一日も早く治すには、医療機関での適切な治療をおすすめします。症状が気になる場合は、早めに受診しましょう。
監修医師からのアドバイス
花粉症は重症化すると日中の眠気や集中力の低下などを引き起こし、日常生活に影響を与えることがあります。外出ができなくなったり、副鼻腔炎を併発して花粉症の時期がすぎてもつらい症状に悩まされたりするケースは少なくありません。
花粉症は今回ご紹介したように食べ物に注意するなど日常生活を改善すれば、予防や症状の改善を期待できる病気です。しかし、どんなに対策をしても症状に悩まされる場合は適切な治療が必要となります。
軽度な症状であれば、目薬や飲み薬などで症状を抑えてやりすごすことができます。しかし、重症な場合には花粉症を治すための減感作療法などの治療を受けることが可能です。
つらい症状があるときは自己流の対策だけではなく、医師に相談して医学的な治療を受けるようにしましょう。












































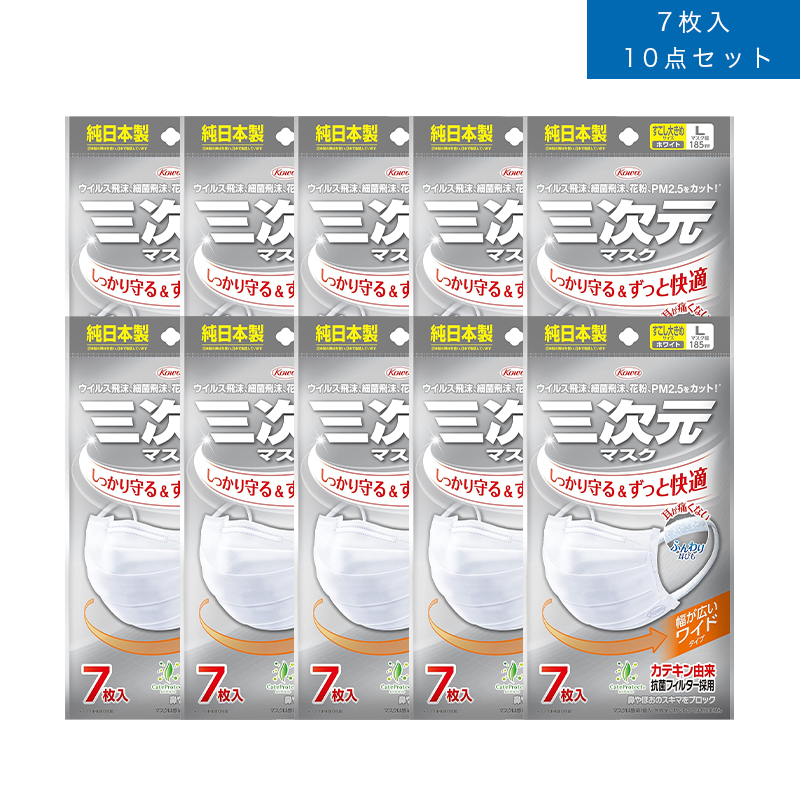

























各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。