野菜に含まれる栄養素と含まれる野菜
野菜は毎日の食生活に欠かせない食材で、ビタミンやミネラル、食物繊維などが含まれています。
野菜に含まれる代表的なビタミンのビタミンAとビタミンCをピックアップし、どんな野菜に含まれているか解説します。
代表的なビタミンやミネラル、食物繊維の特徴と含まれる野菜をみていきましょう。
ビタミン
ビタミンは体内ではほとんど作られないため、食物からとる必要があります。水に溶ける性質の水溶性ビタミンと、脂に溶ける性質の脂溶性ビタミンに分類されます。
- ・ 脂溶性ビタミン:ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK
- ・ 水溶性ビタミン:ビタミンB群(B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ビタミンC
ビタミンA(β-カロテン)を含む野菜
ビタミンAは食品中にβ-カロテンとして含まれ、緑黄色野菜に多く含まれています。「プロビタミンA」とも呼ばれ、体内で必要な分だけビタミンAに変化するのが特徴です。脂溶性であるため、油で炒めたり、ドレッシングをかけたりして食べると吸収されやすくなります。
- ・ にんじん
- ・ ほうれん草
- ・ にら
- ・ こまつな
- ・ かぼちゃ
ビタミンCを含む野菜
ビタミンCは水溶性ビタミンで、熱に弱い性質です。調理の際は水にさらす時間を短くし、加熱しすぎないよう注意が必要です。
ミネラル
ミネラルはカリウム、カルシウム、鉄などの栄養成分で、数は16種類あります。互いに影響し合うためバランスのよい摂取が大切です。カリウムとカルシウムを含む野菜をみていきましょう。
カリウムを含む野菜
カリウムは水に溶けやすい性質であるため、短時間で調理するようにしましょう。
カルシウムを含む野菜
カルシウムといえば、チーズや牛乳などの乳製品を思い浮かべる人は多いでしょう。実は野菜にも含まれています。
食物繊維
「第6の栄養素」と言われる成分です。大切な栄養素ですが、日本人の摂取量は減少しているとの報告があります。食の欧米化が原因の一つと考えられます。
- ・ 干しわらび
- ・ 干しぜんまい
- ・ ドライトマト切り干し大根
- ・ ごぼう
野菜不足の何がいけないの?
野菜が不足すると、栄養のバランスが崩れてしまいます。一時的な野菜不足は心がけ次第で解消できますが、習慣化するとからだや生活に変化をもたらす場合も。
野菜不足が続くと、食事のバランスが偏り、脂質や糖質をとりすぎる可能性があります。ご飯や麺類、肉類でおなかがいっぱいになり、肝心な野菜が入らなくなる場合もあるでしょう。結果的にビタミンやミネラル、食物繊維が不足してしまうのです。必要な栄養が不足すると、スッキリした朝を迎えられず、からだが重く感じたり、鏡に向かうのも億劫になってしまうかもしれません。メイクもうまくのらないでしょう。野菜は健やかでキレイな毎日を送るための大切なサポーターなのです。
1日に必要な野菜の量はどれくらい?
健康日本21では、健康的な生活を維持するための野菜摂取量の目標値を「1日あたり350g以上」としています。令和元年国民健康・栄養調査報告によると、野菜摂取量の平均値は男性で288.3g、女性で273.6gでした。男女とも目標には約70g不足している状況です。野菜は意識してとる必要がありますね。
とはいえ、どれだけ食べればよいのかわからない方も多いでしょう。メニュー例は「食事バランスガイド」を参考にしてみてはいかがでしょうか。食事バランスガイドは厚生労働省と農林水産省で策定した、「何を」「どれだけ」食べたらよいかを示したフードガイドです。野菜はきのこ、豆、いも、海藻を含めた「副菜」となり、1日5~6皿が摂取目安です。次の中から組み合わせてみるとよいでしょう。
- ・ 野菜サラダ
- ・ きゅうりとわかめの酢の物
- ・ 具だくさん味噌汁
- ・ ほうれん草のお浸し
- ・ 煮豆
- ・ きのこソテー
- ・ 野菜の煮物(2皿分)
- ・ 野菜炒め(2皿分)
- ・ いもの煮っころがし(2皿分)
参照:令和元年国民健康・栄養調査結果の概要/厚生労働省
参照:健康日本21(栄養・食生活)/厚生労働省
参照:食事バランスガイドで実践「毎日の食生活チェックブック」/厚生労働省・農林水産省
現代人が野菜不足になる原因
農林水産省の「野菜の消費をめぐる状況について」では、食生活の多様化や食の外部化・簡便化、「野菜を食べているつもり」の意識が、野菜消費の減少要因と分析しています。それぞれ解説していきます。
食生活の多様化
白菜、大根の消費量の減少や肉類の摂取の増加、サラダ消費の増加など食生活の多様化があげられています。白菜、大根の消費量の減少は、野菜を煮物にして食べる機会が減少しているためと考えられます。煮物に代わってサラダの摂取量は増えていますが、サラダは生で食べる機会が多く、カサは減らず多くの量を摂取できないのです。
食の外部化・簡便化
ライフスタイルの変化により、外食したり中食※を利用したりする機会が増えています。自分で手間をかけずに簡単に済ませられ、一人暮らしの方や忙しい方には便利です。しかし野菜が不足しやすくなります。野菜のおかずを一品加えたり、野菜が中心のメイン料理を選んだりして意識する必要があるでしょう。
※中食とは:コンビニやスーパーでお弁当や惣菜を購入したり、外食店のデリバリーを利用したりして食べる食事のこと
野菜を食べているつもり
日本人の野菜摂取の平均値は、厚生労働省が掲げる350g以下です。ところが、「野菜を十分にとっている」「だいたいとれている」として、野菜不足の認識がない人が多いのです。
参照:野菜の消費をめぐる状況について/農林水産省
野菜不足を改善する方法

野菜不足を改善するためには、まずは「毎食1皿」を意識するようにしましょう。摂取量を増やす工夫を紹介します。
加熱して食べる
野菜は加熱するとカサが減るため、摂取量を増やせます。水溶性ビタミンを含む野菜は、ゆでると栄養成分が損失してしまうため、電子レンジ調理や煮物、スープ料理がおすすめです。具だくさんの味噌汁やポトフがよいでしょう。
カット野菜や冷凍野菜を利用する
一人暮らしの方やあまり料理をしない方は、野菜を余らせてしまう場合があるかもしれません。カット野菜や冷凍野菜の利用がおすすめです。冷凍野菜は電子レンジ調理で食べられる野菜もあり、手軽に食べられます。冷凍庫に常備しておくとよいでしょう。
外食やコンビニ食に野菜料理をプラスする
外食やコンビニ食が多い方は、野菜を1品加えるようにしましょう。外食の場合は小鉢のついた和定食にしたり、付け合わせの野菜は残さず食べたりなど工夫してみましょう。おにぎりがメインとなる場合は、サラダや調理済みの野菜のおかずを加えてみてください。
毎日の食事に野菜をもう1皿プラスしよう
野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維など美容と健康に欠かせない成分が含まれています。しかし、からだに大切だとわかっていても、十分に摂取できていない傾向です。野菜不足の認識を持ち、毎食1皿は野菜をとるようにしましょう。また、旬の野菜は栄養価が高いと言われているので、旬の野菜をとり入れるのもおすすめです。
さまざまな野菜から栄養素をまんべんなくとり入れ、はつらつした毎日、キレイな毎日を過ごしましょう。












































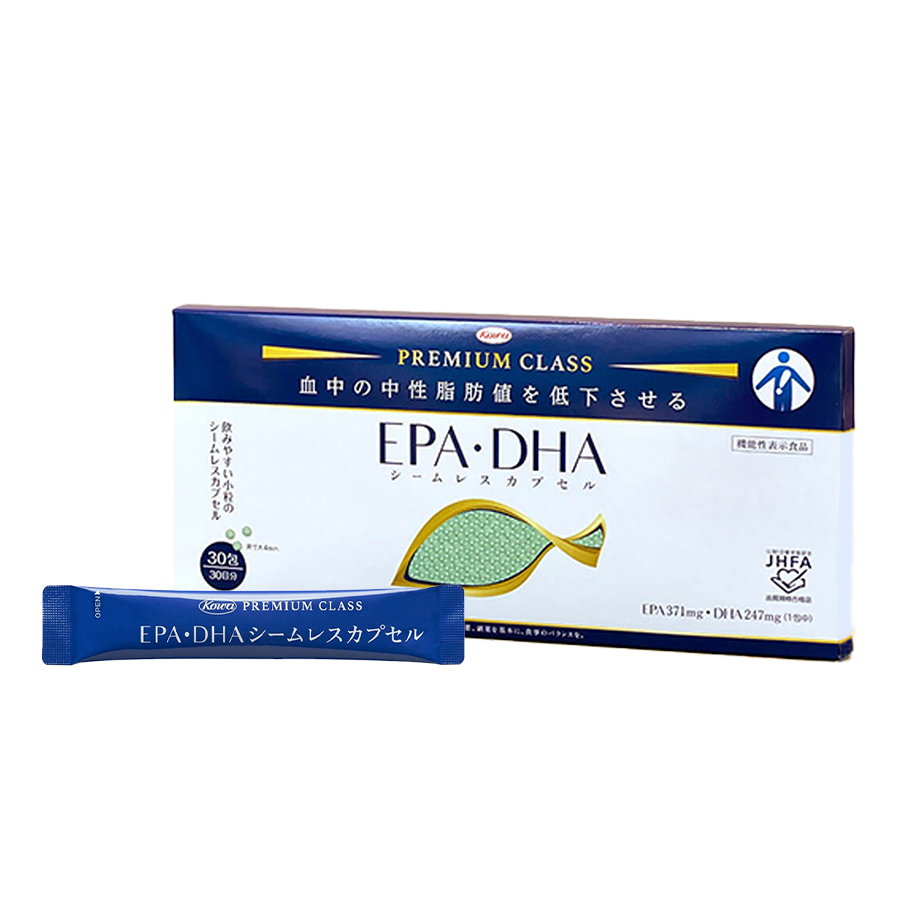

























各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。