セラピストライター白井未奈子
サービス業を10年経験するなかで、リラクゼーション業務に出会い「人を癒す」ことに目覚める。
フリーランスに転向して以降は、ボディートリートメントとフェイシャルエステの知識を活かし、美容・健康系の記事執筆を中心に担当。今は手ではなく、文章で読者にくつろぎとすこやかさを届けることを目指している。
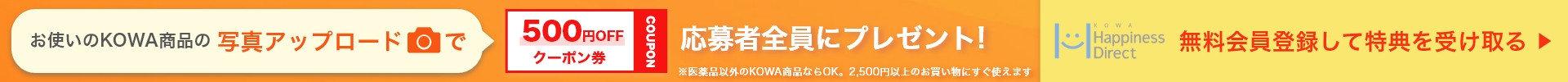


自律神経を整えるためのツボは、頭・耳・背中・足裏といった全身のいたるところにあります。「合谷(ごうこく)」や「内関(ないかん)」といったツボは、手にあると知っている人もいるのではないでしょうか?
ツボは全身の内臓や神経につながっているため、刺激するとめまい・吐き気・肩こりといった不調にはたらきかけることができます。心身のバランスを崩しやすい季節の変わり目に、アプローチするべき場所と注意点をしっかり確認しましょう。
春や秋、季節の変わり目に不調をおぼえる方は多いです。「病院に行くほどツラくはないけれど、なんとなくスッキリしない…」といった場合は、自律神経が関係しているのかもしれません。自律神経が乱れやすくなる原因と、心身への影響をチェックしてみましょう。
仕事・家事・育児・介護だけでなく、更年期といった加齢による影響も、自律神経を乱れさせる一因に数えられています。とくに変化の年にあたる30~40代の女性が不調をおぼえやすくなるのも、少なからず自律神経が関係しているといえるでしょう。
そもそもツボ押しとは、指で押して刺激するケア方法のひとつです。素人でも手軽に取り組めますが、自律神経をはじめとする各部位に通じているからこそ、やみくもに刺激してはいけません。
おぼえておきたいツボ押しの注意点を3つご紹介します。
ツボ押しは、痛いと思うほど強くしすぎてはいけません。刺激しすぎると副交感神経を優位にしたいのに、かえって交感神経を優位にしてしまうおそれがあるためです。さらに、いずれのツボも皮膚の表面に近いところにあります。痛気持ちいい力加減で十分届くでしょう。
ツボ押しをするときは、深呼吸をしてなるべくリラックス状態で行うと吉です。間違っても息を止めてはいけません。吸う時間に対し、吐く時間を2倍くらいに伸ばせると、副交感神経を優位にもっていけます。ツボ押しを効率的に行うために心がけてみてください。
ツボを押したあとは、水分をたっぷり摂るのも大切です。ツボ押しは心身にアプローチするだけでなく、めぐりをよくし、溜まった老廃物を押し流すはたらきもしてくれます。スムーズに循環させるために、胃腸への負担が少ない常温水もしくは白湯を飲みましょう。
自律神経の乱れからくる不調は、真っ先に首のうしろや頭に現れるといわれています。まず、頭・首・耳にあるツボをチェックしてみましょう。
百会は、頭のてっぺん、ちょうどつむじ辺りにあるツボです。副交感神経にアプローチできるため、イライラ感が気になる方におすすめ。押すと全身のめぐりがよくなるともいわれているため、手足がポカポカとするのを感じるでしょう。
天柱は、首のうしろ、頭と首の境目付近にあるツボです。首のうしろには太い筋肉が2本とおっていて、その中心にあるくぼみのほぼ真上にあります。肩こり・頭痛・疲労感などに悩んでいるときに、押してみてください。
天柱のすぐ隣、首のうしろにあるくぼみのやや外側にあるのが風池です。くぼみのてっぺんと耳を直線で結んだときに、中間くらいのところにあります。めぐりの悪さからくる、ふわふわのめまいが気になる方は押してみましょう。
完骨は、自律神経を乱れさせる三半規管の不調にアプローチできるツボです。耳のうしろにある、でっぱった骨の後方にあります。めまいのほか、寒暖差・気圧変動により起こる頭痛、乗り物酔いにお悩みの方におすすめです。
自律神経の乱れからくるめまいをやわらげたいなら、完骨と同じく耳にある翳風も押してみてください。耳たぶのうしろにあるくぼみに位置しています。押すとあご周辺に鈍い痛みを感じるでしょう。

数あるツボのうち、最も手軽に刺激できるのが手にあるツボです。手のひらをはじめ、手首や腕にもあります。自律神経を整えるのをサポートしてくれる手のツボをみてみましょう。
万能のツボと呼ばれるのが、親指と人差し指の付け根にある合谷です。両指の骨がちょうど交わるポイントにあり、挟むように押すとじんわり痛みが走ります。肩こりや頭痛をはじめ、不調がみられるときには押してみる価値ありです。
労宮は、手のひらの真ん中あたり、中指と薬指のちょうど間にあるツボです。疲労が溜まる場所を意味するため、押すと疲労感をやわらげてくれるでしょう。イライラや不安感、緊張といった精神の不安定さを感じる方にもおすすめです。
神の門と書く神門は、精神的なエネルギーを司るツボです。手首の内側のしわの上、小指の下のラインに位置していて、主に心の不調に効くといわれています。イライラ・うつうつ感のほか、動悸、吐き気といった消化器トラブルに悩む方におすすめです。
不安や緊張からくる吐き気を緩和するといわれるツボが、手首にある内関です。手首のシワから数えて指3本分下、腕の内側の真ん中に位置しています。合谷についで万能のツボといわれているので、ぜひ押してみてください。
手首のシワから指三本分下、内関のちょうど裏側にあるのが外関です。ふわふわのめまいのほか、頭痛や疲労感の軽減に役立つと知られています。三半規管があまり強くない方は、親指と人差し指で挟むように内関とセットで刺激するとよいでしょう。
自律神経の乱れによる影響のうち、おなかや心まわりの不調は、不調がみられる場所と重なる部分を刺激してあげるのもおすすめです。背中と胸元にあるツボをみていきましょう。
肝兪は、東洋医学でいうところの五臓六腑に通じるツボです。とくに胃とのつながりが深く、吐き気や疲労感・消化器トラブルによいとされています。場所は肩甲骨の一番下の部分から背骨を辿ったときにある、太い筋肉の上です。
うつうつ感や動悸といった、心に不調が現れるときは、胸元にあるだん中を刺激してみましょう。両側の乳首を結んだちょうど真ん中、胸骨の上にあります。胸のつかえ感があるときもぜひ押してみてください。
足や足裏には、消化器の調子にアプローチするツボがたくさんあります。自律神経の乱れが胃腸に現れやすい方は、次の3つのツボを刺激してみてください。
足三里は、消化器トラブルにはたらくとされる代表的なツボです。ひざの内側、お皿の最下部から指4本分下にあります。吐き気や腹痛のほか、足や歯のトラブルにも役立つでしょう。
太衝は、足の甲、親指と人差し指の骨が交わるところにあるツボです。怒りの感情にはたらきかけるツボなので、イライラ感が強いときに押してみてください。押すとめぐりもよくなり、ポカポカ感が得られるでしょう。
消化器の調子を整えるには、足裏にある湧泉も有力候補です。自律神経を整えるのを手助けしてくれて、倦怠感にアプローチできます。下半身のめぐりをよくしてくれるので、足のむくみや疲労感にお悩みの方にもおすすめです。
自律神経を整えるためのツボ押しをするときは、なるべく副交感神経を優位にしやすいよう、リラックスして行うと効率的です。心身をリラックスさせるためのセルフケアとしては、次のようなものがあります。ツボ押しの前後に取り組んでみましょう。
・ 睡眠の質を上げる(朝日を浴びる、睡眠環境を整える)
・ 朝ごはんをしっかり食べる
・ お風呂にゆっくり浸かる
・ ストレッチといった適度な運動をする
・ アロマテラピー・音楽を聴く
・ マッサージをする
ツボ押しの流れに組み込みやすいのが、耳のマッサージです。親指と人差し指で、両耳の上下左右を順番につまんでいくだけ。1分ほど続けるとめぐりがよくなり、耳全体がポカポカとする感覚を得られるでしょう。春秋のセルフケアにぜひ実践してみてください。
各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。