メディア機器の普及による目への悪影響
近年、メディア機器の使用が当たり前となり、暮らしの利便性や仕事の効率化が向上する一方で、目にトラブルを抱える人が増加。目の疲れが一時的であれば、休息によって症状は緩和しますが、疲れ目を放置すると症状が悪化してしまいます。眼精疲労を生じ、頭痛や肩こりまで引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
メディア機器の使用による眼精疲労の原因と症状
「至近距離で画面を見続ける」「同じ姿勢で作業を続ける」「ブルーライトを浴び続ける」といった状況は、眼精疲労を引き起こしやすくなります。休んでも目の疲れがとれないだけでなく、目の痛みや頭痛・肩こりなど、全身にまで影響が出て回復しにくくなってしまうでしょう。
至近距離で画面を見続ける
メディア機器の画面に目を近づけて長時間過ごしていると、目の筋肉に負担がかかり、ピント調節機能が低下。無理なピント合わせや目の緊張が続く状態は、目の痛みや頭痛を引き起こしやすくなります。
同じ姿勢で作業を続ける
長時間同じ姿勢を続けていると、首から肩にかけての筋肉が緊張し続けます。筋肉疲労が生じて血の流れが悪くなり、首・肩のこりや痛みの原因になるのです。
ブルーライトの強い光を浴び続ける
メディア機器から発せられるブルーライトは、可視光線(目で見える光)の中でも最も波長が短く、強いエネルギーを持つ光です。角膜や水晶体で吸収されずに直接網膜まで到達するため、長時間浴びると網膜にダメージを与えるリスクが高まります。
メディア機器の見過ぎであらわれる目の症状
メディア機器の見過ぎは、目に大きな影響を及ぼします。ドライアイやピント調節機能の低下を引き起こし、さらには近視になるリスクも高めてしまうのです。
ドライアイ
長い時間画面を見続けると、まばたきの回数が極端に減り、目の表面を潤す涙の分泌量が減少します。すると、目が乾燥して角膜が傷つきやすい状態になるのです。ドライアイになると、目の乾燥だけでなく、ゴロゴロとした異物感が生じます。また、目のかすみ・まぶしさ・疲れ・赤み、涙や目やにが出る、見えにくいといった多岐にわたる症状を引き起こしてしまうでしょう。
ピント調節しにくくなる
メディア機器を至近距離で見続け、あまり目を動かさずに過ごしていると、「眼球を内側に寄せる筋肉」「ピントを調節する筋肉」「瞳を動かす筋肉」の緊張状態が続きます。筋肉疲労により3つの筋肉のバランスが乱れ、ピント調節がうまくできなくなってしまうのです。いわゆる「スマホ疲れ」や「スマホ老眼」と呼ばれる、目が疲れてぼやっと見えてしまう症状を引き起こします。
近視が進行しやすい
30cm以下の至近距離で物を見ると、近視の割合が2.5倍増えるとされています。メディア機器を使用する際は、20cmほどの近い距離で見るケースも多く、使用時間が長くなるほど、近視を促進させやすくなってしまうのです。
メディア機器と上手に付き合う9つの方法

スマホやパソコンによる目への悪影響を抑えるには、メディア機器の使い方に工夫が必要です。
とくに、子どものインターネット利用時間の増加にともなう視力低下は、近年問題視されています。裸眼視力が1.0未満の子どもの割合は、小学校で3割超え、中学校で約6割、高等学校で約7割と、学年が上がるにつれて増加傾向です。子どもの視力が低下しないように、メディア機器との付き合い方を見直してみましょう。すぐに実践できるシンプルな方法をお伝えしますので、ぜひ試してみてください。
1.適度に目を休める
メディア機器を使用する際は1時間ごとに小休憩をはさみ、目を休ませてください。メディア機器を見ているときは、まばたきの回数が減り、まばたきをしても目が完全に閉じない状態を生じやすくなります。まぶたをしっかり閉じて、回数を増やすように心がけるのも大事です。
参照:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて/厚生労働省
2.画面や部屋の明るさを調節する
メディア機器の画面が明る過ぎると、眩しさを感じやすくなります。部屋を明るくして、画面の輝度は抑えめに調節しましょう。
3.目と画面の距離は40cm以上とる
物を近くで見続けると目が緊張状態になり、疲れやすくなります。とくに、画面が小さいスマホやゲーム機器は、より疲れを感じやすい状態に。集中すると画面に目が近づいてしまう傾向があるため、画面から40cm以上目を離すように意識しましょう。また、上を向いて画面を見ると目が乾燥しやすいので、視線を見下ろす位置に画面を配置してください。
参照:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて/厚生労働省
4.正しい姿勢で座る
椅子の背もたれに、背中をつけて深く座りましょう。肘は直角、膝は床から90度になるようにして、身長が低い方は座布団や足台を使用して調節してください。正しい姿勢を習慣化すると、目の疲れを引き起こしにくくなります。
5.ブルーライトカットメガネやフィルムを使用する
ブルーライトの影響をやわらげるには、できるだけ光を遮る必要があります。ブルーライトのカット効果があるメガネや、スマホやパソコン画面に貼るブルーライトカットフィルムなどを使用しましょう。
6.目をあたためる
目が疲れたと感じたら、あたためてみましょう。血流がよくなり、目のまわりの筋肉がほぐれてリラックスできます。市販のホットアイマスクやホットタオルを使用すると、手軽に目をあたためられるのでおすすめです。
7.睡眠時間を十分にとる
目の疲れを回復させるには、睡眠が欠かせません。疲れ目から眼精疲労へ進行しないようにするためにも、しっかり睡眠時間を確保してください。また、睡眠の質を上げる工夫も大切です。寝る1時間前からはメディア機器の使用を控えると、眠りにつきやすく、睡眠の質を向上できます。
参照:良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと/厚生労働省
8.目薬を使用する
目の疲れの症状に対応した目薬を使用してみましょう。ただし、目が疲れたからと目薬をさし過ぎると、必要な成分まで流されてしまいます。また、薬の成分が残って角膜が傷つく原因にもなるため、目薬を使用する際は用法・用量を守ってください。
9.サプリメントや栄養ドリンクを活用する
目の疲れが気になるときや、多忙でなかなか目を休める時間がとれないときは、サプリメントや栄養ドリンクに頼るのも一つの方法です。職場や自宅に常備しておくと、いざというときに役立ちます。
デジタルデトックスしてみよう
スマホ・タブレット・パソコンなどのメディア機器を使用する際は、時間を決めて、目を休める時間を意識的につくりましょう。忙しい日常から離れ、自然に囲まれた環境でリラックスするのも目の回復に役立ちます。メディア機器は日常的に欠かせないからこそ、健康的に使い続けるためには、適度な休憩が必要です。ぜひ実践して、メディア機器と上手に付き合ってください。











































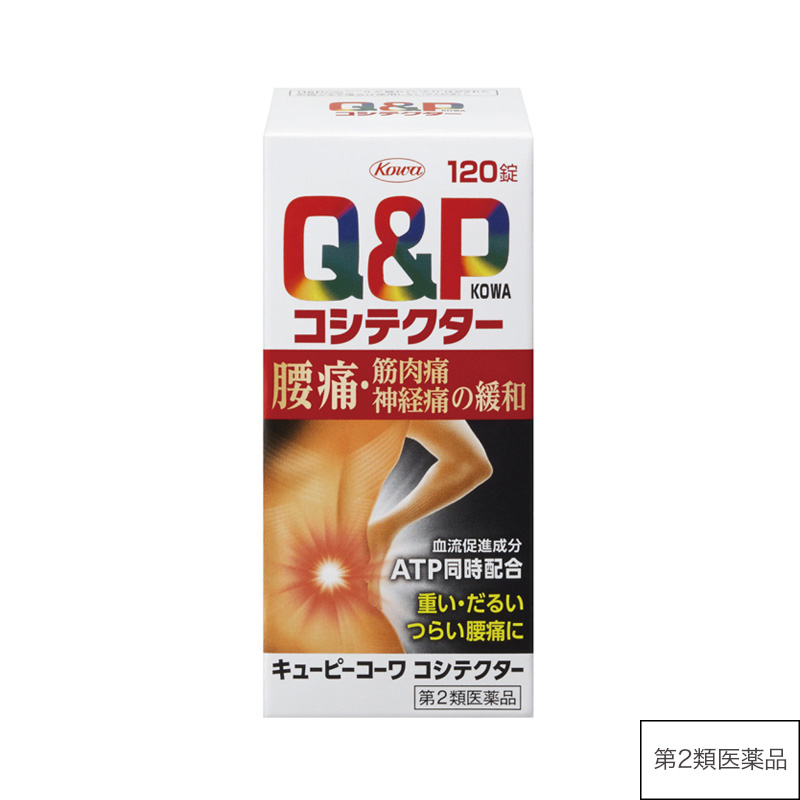






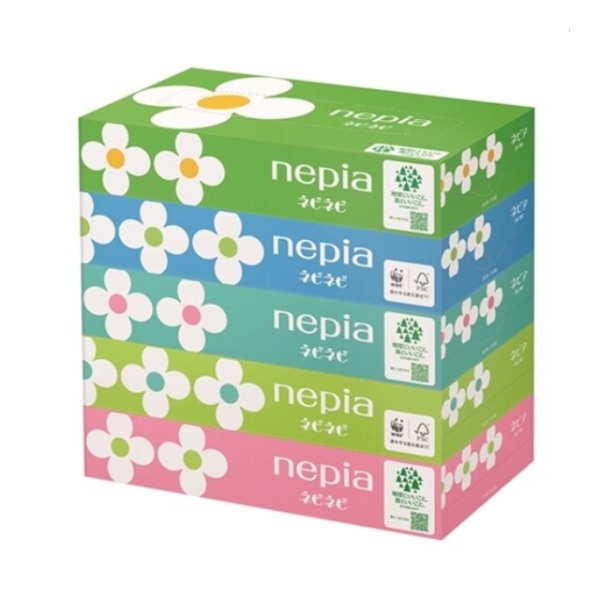
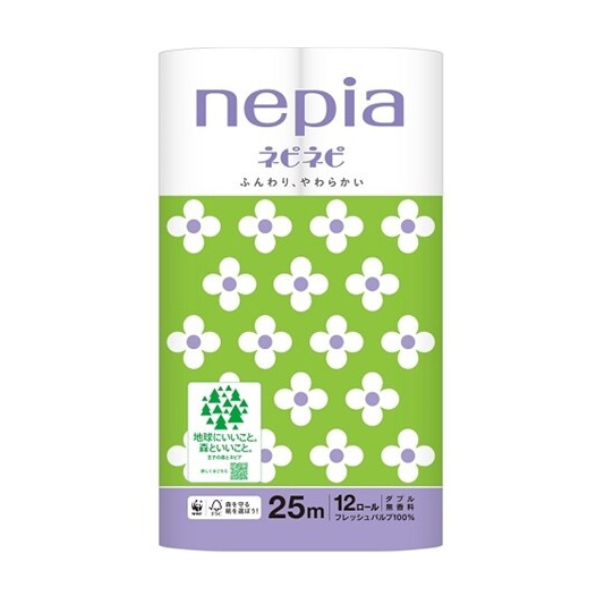

















各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。